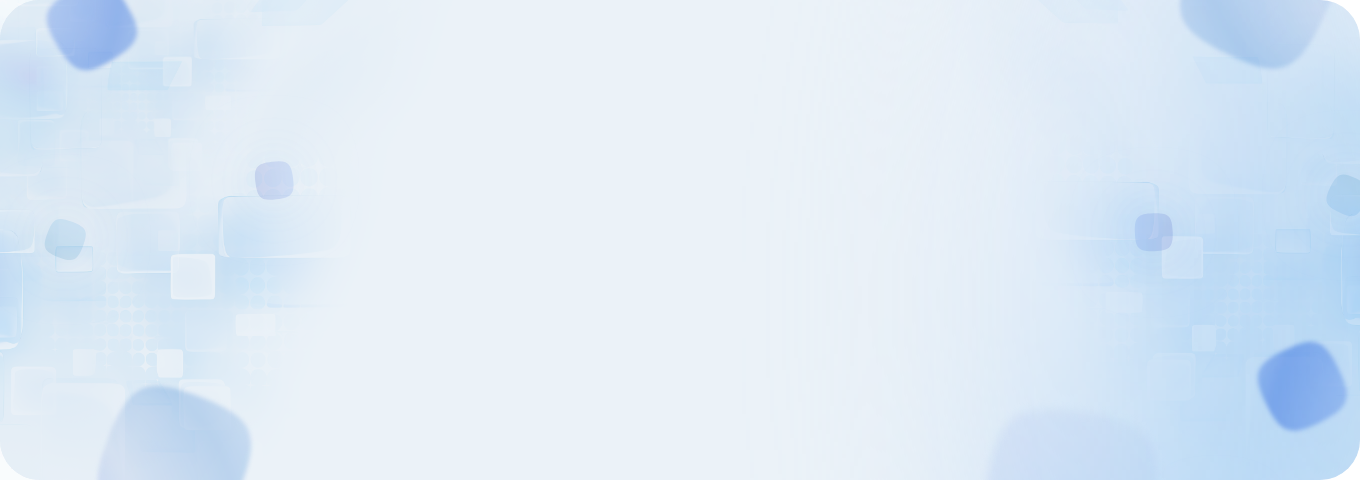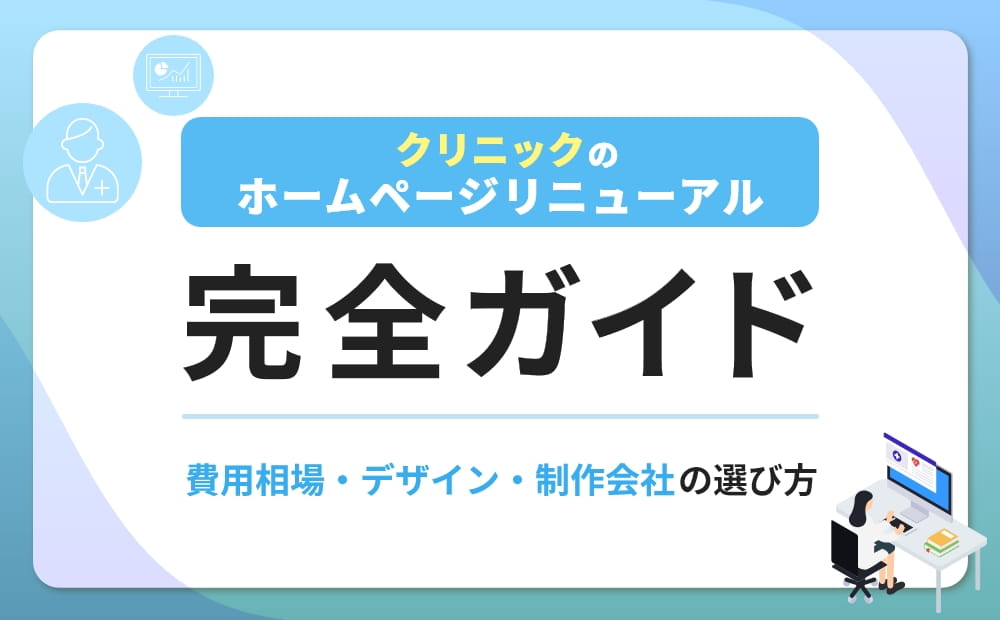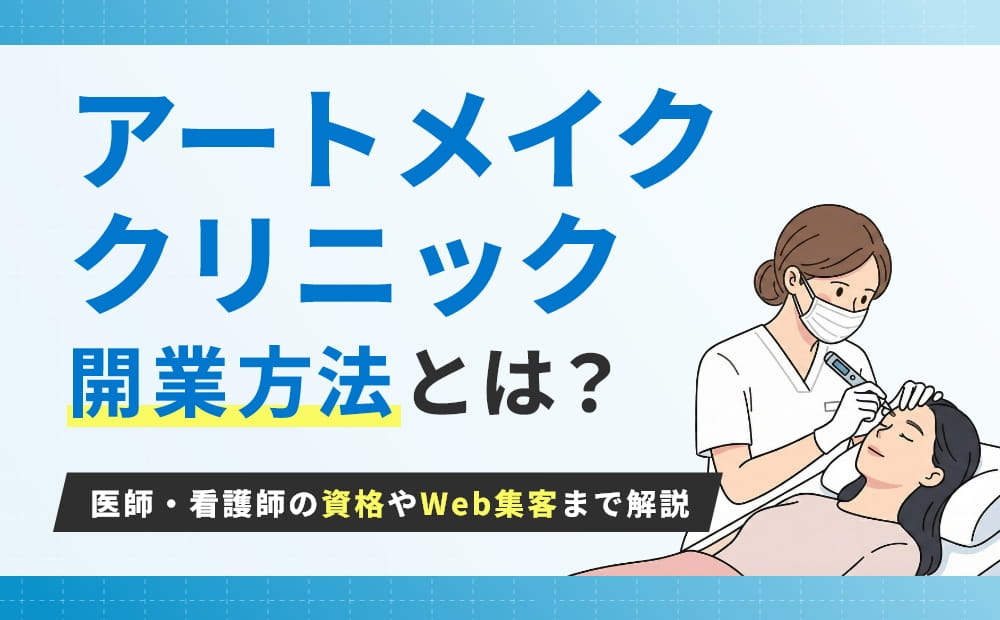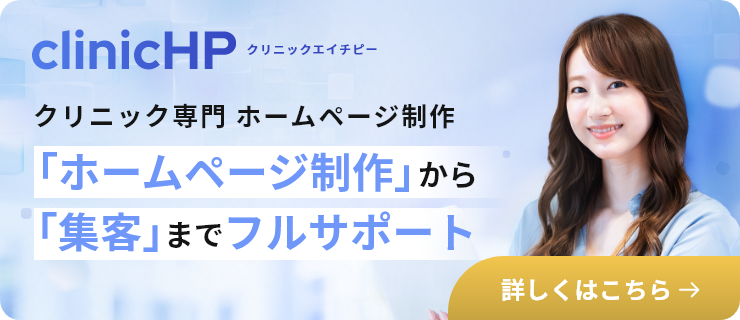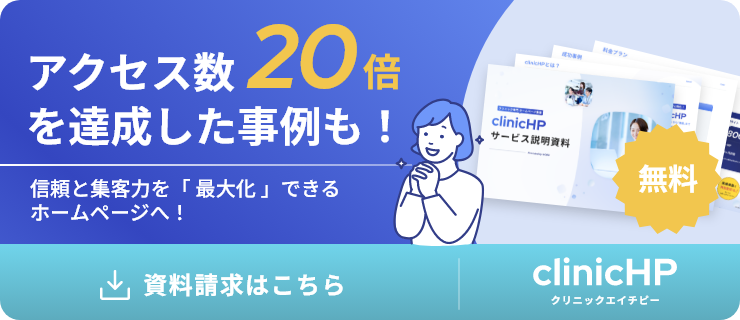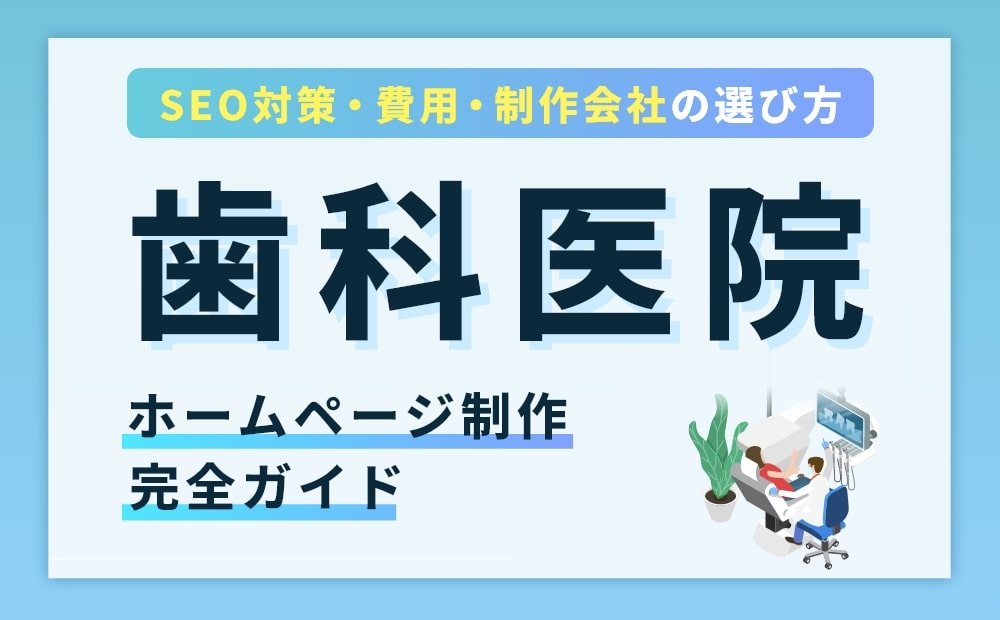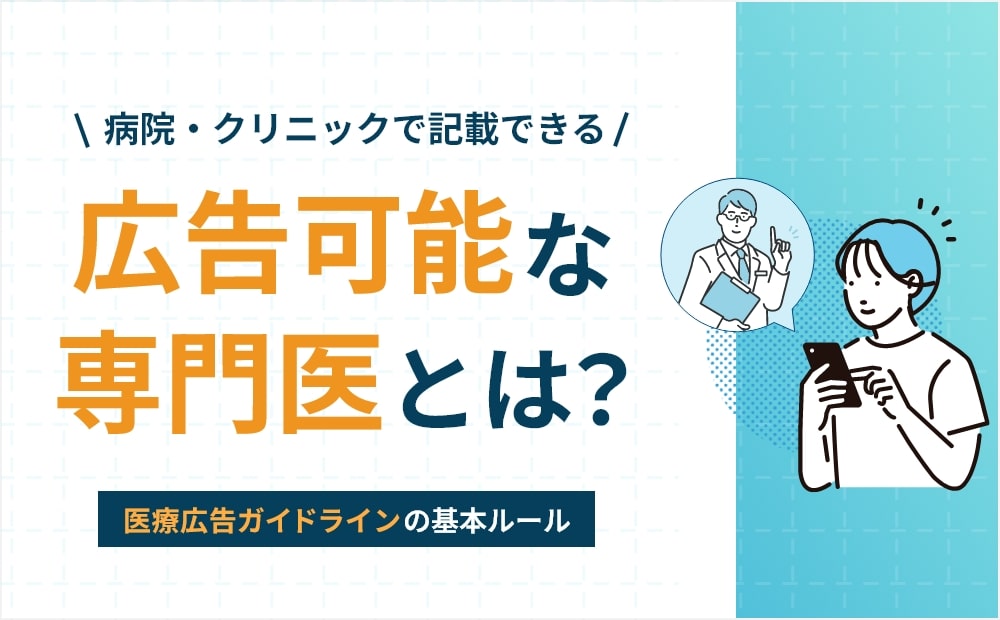医療広告のNGルール解説|若返り・アンチエイジング表現はOK?
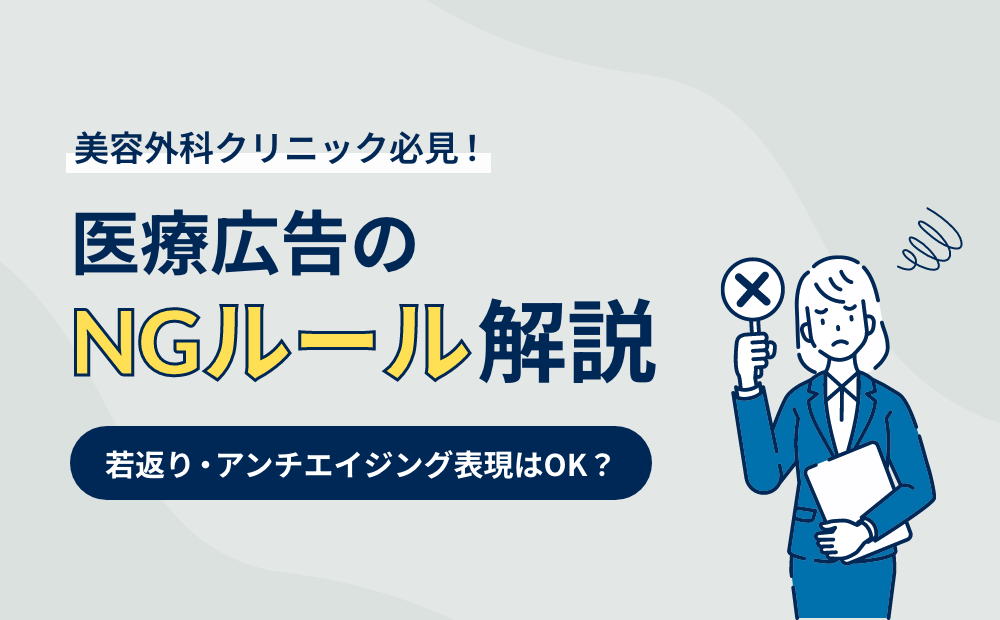
「若返り」や「アンチエイジング」といった言葉は、美容クリニックでの訴求において人気が高い表現です。しかし、医療広告ガイドラインの視点から見ると、これらの言葉を安易に使うことにはリスクが伴います。「使っても大丈夫なのか」「どの程度までなら許容されるのか」と迷われる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、医療広告ガイドラインの基本的な考え方から、「若返り」表現に関する注意点、安全に情報を発信するための工夫、さらには「限定解除」の活用方法までを具体的に解説します。自院の広告やホームページで、リスクを避けながらユーザーに伝わる表現をしたい方に向けた実践的な内容です。
目次
医療広告ガイドラインの背景と基本ルール
美容医療の分野では、広告やホームページ上の表現が厳しく規制されるようになっています。特に「若返り」「アンチエイジング」といった言葉は、多くの人に響きやすい一方で、誤解を生む可能性があるため注意が必要です。
医療広告ガイドラインとは、医療機関が広告やホームページを通じて発信する内容について、利用者の誤解や過度な期待を避けるために定められた厚生労働省の基準です。特に2018年の制度改正により、従来は対象外だったホームページも広告と同様に規制の対象となりました。
この改正の背景には、美容医療に関するトラブルが増加していたことが挙げられます。たとえば、施術前後の写真を使って効果を強調したり、個人の感想を掲載して誤認を招いたりするケースが問題視されてきました。その結果、Web上の表現にも明確なルールが課されるようになったのです。
「若返り」や「アンチエイジング」がNGな理由

「若返り」や「アンチエイジング」という言葉は、多くの人にとって魅力的に映りますが、医療広告ガイドラインでは使用を控えるべき表現とされています。その理由は、これらの言葉が効果を保証するかのような印象を与える恐れがあるためです。
たとえば、「〇歳若く見える」「20代の肌に戻る」といった言い回しは、結果を断定する表現とされ、優良誤認にあたるリスクが高いと判断されます。また、こうした表現の多くは、公的医療保険の対象外であり、科学的な裏付けが十分とは言えないことも問題視されています。実際には、加齢へのアプローチには個人差が大きく、確実な効果を一律に示すことはできません。広告にこれらの表現を用いる場合は、十分な配慮が求められます。
とはいえ、現時点では検索結果のタイトルや大手サイトでも「アンチエイジング」や「若返り治療」といった表現は依然として多く見られます。これは、これらの言葉が明確に禁止されているわけではなく、文脈や条件によっては情報提供として扱える「グレーゾーン」に位置づけられているためです。
他にも注意が必要なNG表現の一覧
医療広告ガイドラインで制限されている表現は、「若返り」だけに限りません。たとえば、「絶対に安全」「芸能人も通っている」「満足度100%」といった根拠のない主張は、すべてNG表現に該当します。また、「当院が最も効果的」「他院より優れている」といった比較表現も禁止です。
さらに、「副作用は一切ない」「痛みがまったくない」などの断定的な表現も、医療行為に対する誤解を生む可能性があり、使用は避けるべきとされています。これらの表現を含んだ広告は、行政からの指導やネット上での指摘を受ける可能性があり、信頼性の低下や評判リスクにもつながります。制作の段階で、こうした表現をあらかじめ避けておくことが重要です。
若返り表現の使い方と限定解除の工夫

「若返り」や「アンチエイジング」といった言葉を広告やホームページで使いたい場合、医療広告ガイドラインに違反しないための工夫が欠かせません。広告規制の例外となる「限定解除」の仕組みや、具体的な言い換えの方法、媒体ごとに異なる運用ルールにどう対応すべきかを紹介します。訴求力を損なわず、安全に情報を届けるためのヒントをまとめています。
「限定解除」とは何か
「限定解除」とは、患者が自発的にアクセスした情報に対しては、医療広告ガイドラインの一部が適用除外となる仕組みのことです。たとえば、クリニックの公式ホームページや、来院時に配布する資料など、本人が自ら求めて入手した情報が該当します。
この考え方は、「広告」と「自主的な情報収集」を区別するという前提に基づいています。ただし、限定解除の適用を受けるには条件があり、治療内容・費用・副作用・問い合わせ先など、所定の情報を正しく記載しておくことが前提です。ルールを理解して適切に対応すれば、表現の幅を広げることも可能です。
限定解除の対象となる情報とは
限定解除を活用するには、ページ内に一定の情報をもれなく記載する必要があります。具体的には、以下の項目が求められます。
- 連絡先(誰でも問い合わせ可能な内容)
- 診療の内容と方法
- 治療費の明示(消費税の表示も含む)
- 副作用やリスクについての説明(施術ごとに個別記載)
これらはいずれも厚生労働省が定めた項目であり、ひとつでも抜けていれば限定解除は認められません。また、専門用語ばかりでなく、一般の方にも伝わる言葉で記述することも重要です。正確でわかりやすい情報を整えることが、リスク回避と表現の自由度を両立するための土台となります。
「若返り」表現を使いたい時の3つの工夫
「若返り」という言葉をどうしても使いたい時は、表現を見直すことでガイドラインに沿った訴求が可能です。具体的には、以下の3つの工夫が効果的です。
- 「若返る」と断定せず、「若く見える印象を目指す」など視覚的・印象的な表現に置き換える。
- 「エイジングケア」「年齢に応じた美容ケア」など、機能性を示す代替語を使う。
- 限定解除の条件を満たしたページ内で、「患者の要望に合わせた施術例」などを中立的に紹介する。
これらを適切に組み合わせることで、ユーザーの関心に応えながらも、ルールを守った表現が可能になります。
Yahoo!広告などの媒体別ルールも把握
広告を出稿する際には、使用する媒体ごとに異なるルールがあることにも注意しておきたいところです。Yahoo!広告では2019年以降、自由診療を訴求する場合には「保険適用外であること」と「標準的な費用」の記載を、広告のテキストやバナーそのものに含めることが必須とされています。
以前はリンク先に記載されていれば差し支えないとされていましたが、現在は広告クリエイティブの中で情報を明確に示すことが求められています。このように、各媒体は独自の審査基準を設けており、変更されることも少なくありません。
自院のサイトや広告で使える対策集

医療広告ガイドラインを理解した上で、安全にかつ効果的に情報発信を行うには、日々の運用に取り入れられる対策が欠かせません。自院のホームページや広告で注意すべきポイントを整理し、リスクを避けながら訴求力を高めるための方法を紹介します。
特に「若返り」などの表現を使用したい場合に、どのような工夫や準備が必要か、実践的な視点からお伝えしていきます。
すぐにできる!表現チェックの手順
医療広告ガイドラインに違反しないためには、まず現在使っている表現を客観的に見直すことが重要です。特に確認したいのは、次の3つのポイントです。
- 効果を断定する表現がないか
- 他院との比較を示していないか
- 体験談を使用していないか
これらをチェックリストとしてまとめておくことで、日常的な運用でも確認しやすくなります。また、医師や責任者だけでなく、スタッフと共有し、複数人で確認できる体制を整えることもリスク回避につながります。自院だけでの判断が難しい場合は、専門家や制作会社に定期的なチェックを依頼する方法も有効です。
Web制作会社と連携する際の注意点
ホームページや広告制作を外部に依頼する際には、医療広告ガイドラインへの理解があるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。そのうえで、デザインやコピーだけでなく、リンク先の内容やタイトルなど細かな部分にも配慮することで、ガイドラインに沿った表現が実現しやすくなります。
ガイドライン違反によるリスクを再確認
医療広告ガイドラインに違反した場合、その影響は単なるページ修正にとどまりません。厚生労働省や自治体からの指導、ネット監視による指摘、場合によっては行政処分の対象となる可能性もあります。
さらに、違反表現がSNSや口コミサイトなどで拡散されると、クリニックの信頼性が損なわれ、風評被害につながることもあります。しかも、「知らなかった」「意図していなかった」としても、免責されることはありません。定期的な見直しと、ルールに沿った表現づくりは、クリニックの信頼を守るための大切な取り組みです。
それでも若返り訴求したい時の戦略
「若返り」という言葉には高い集客効果がありますが、ガイドライン上では使い方に大きな制約があります。それでも訴求したい場合は、言い回しや表現の切り口を工夫することで、リスクを避けつつ活用する道があります。
たとえば、「自然な印象を目指すケア」「年齢に合わせた肌のお悩み対応」など、具体的なニーズや状態に寄り添った形で表現することがポイントです。また、医師の見解や医学的な説明を添えて、客観的かつ中立的な情報として提示すれば、誤認リスクも下げられます。
医療広告表現の専門家に相談しませんか?

医療広告ガイドラインについての理解を深めたり、表現の工夫を重ねたりしても、実際に運用する中では迷ってしまう場面が出てくるものです。そんな時は、医療広告やWeb制作に詳しい専門家に相談してみるのがおすすめです。不安やリスクを減らしながら、スムーズに対応を進められるようになります。
clinicHPがどのような支援を行っているのか、そして無料相談を活用することで得られる具体的なメリットをご紹介します。
clinicHPのサポート実績と対応領域
clinicHPでは、美容医療クリニック向けに、医療広告ガイドラインを踏まえた広告・ホームページ制作の支援を数多く行ってきました。たとえば、「自由診療の施術をどのように表現すればいいかわからない」といったご相談に対しては、文章表現の見直し、構成の再設計、検索ニーズを意識したキーワード設計など、実務に沿った多面的な対応が可能です。
施術ごとの魅力をしっかり引き出すためのポジショニング設計や、広告媒体ごとの審査基準に合わせた内容調整も、clinicHPが対応している領域です。
医療広告ガイドラインには、解釈に幅があるグレーな部分も少なくありません。そうした判断が難しいケースでも、私たちはクライアント様のご意向や現場の状況を丁寧にうかがいながら、できるだけ訴求力を損なわず、リスクを抑えた表現をご提案しています。
もちろん、すべてを規制に合わせるだけでは、伝えたい想いまで制限されてしまいます。だからこそ、法的なルールを守りながらも、患者さんの心に届くような言葉で魅力を届ける工夫を大切にしています。
無料相談で得られること
clinicHPの無料相談では、現在運用しているホームページや広告表現が医療広告ガイドラインに違反していないか初期診断ができます。診断結果に応じて、表現の見直しポイントや限定解除の適用可否など、実務に沿った具体的な改善提案をご提示します。
ご希望があれば、構成案の再設計や原稿修正の方向性、デザイン面との整合性についてもアドバイスが可能です。初回のご相談から改善のヒントを持ち帰っていただけるよう、実用的なフィードバックを重視しています。

よくある質問
「アンチエイジング」は一切使えない?
「アンチエイジング」は原則として医療広告では避けるべき表現ですが、限定解除が適用される条件を満たしたページであれば、使用できる場合もあります。たとえば、「アンチエイジングに関心のある方に提供している施術」といった文脈で、治療内容の一部として客観的に記述すれば認められるケースもあります。
ただし、効果を保証するような表現や、誤解を与える内容は依然としてNGです。文脈、目的、表現方法の3つの観点から慎重に検討することが大切です。
「若返り治療」は表現できる?
「若返り治療」という表現は非常にあいまいであり、ガイドライン上は使用が難しいとされています。ただし、「肌の印象を整える施術」や「年齢に応じたケア」といった文脈に言い換えることで、限定解除の対象ページ内で表現する余地はあります。
重要なのは、効果を断定せず、医学的な根拠や医師の説明を交えて中立的に伝えることです。表現を見直すことで、法令に抵触することなく、ユーザーの関心に応える情報提供が可能になります。
SNSでの発信にもルールはある?
SNSも、内容によっては「広告」とみなされ、医療広告ガイドラインの適用対象になります。特に、「〇〇で必ず改善」「今だけ割引キャンペーン」などの投稿は注意が必要です。SNSは拡散性が高く、誤解を招く表現が拡がりやすいため、ホームページ以上に慎重な運用が求められます。
また、公式アカウントはもちろん、スタッフが運営する関連アカウントでも、クリニックの情報を発信する場合は広告扱いとなる可能性があります。事前に運用ポリシーや確認体制を整えておきましょう。
ガイドライン違反が発覚するとどうなる?
ガイドライン違反が指摘された場合、厚生労働省や都道府県の担当機関から是正勧告や文書指導を受ける可能性があります。さらに悪質なケースでは、行政処分や公表の対象となる場合もあります。
対応には時間やコストがかかるだけでなく、信頼の低下や炎上リスクにもつながります。「知らなかった」では済まされないため、日頃からチェック体制を整えておくことが、リスクを避けるための最善策です。
専門家に相談する基準は?
「この表現は大丈夫だろうか」「どこまでなら許容されるのか判断が難しい」と感じたら、その時点で専門家に相談するのが賢明です。特にホームページのリニューアルや広告出稿前は、トラブルを未然に防ぐチャンスでもあります。
相談相手は、医療広告ガイドラインに詳しく、法的視点と実務のバランスを理解している制作会社や広告代理店が望ましいです。部分的な相談からでも始められるため、少しでも不安がある場合は早めの行動が安心につながります。
まとめ|表現の工夫で信頼と集患を両立
「若返り」や「アンチエイジング」といった言葉は、多くの方に響きやすい表現ですが、医療広告として用いる際には慎重な対応が求められます。ただし、完全に使えないわけではありません。限定解除の仕組みや言い換えの工夫を取り入れれば、ユーザーに伝わる内容を維持しながら、ガイドラインにも配慮した表現が可能になります。
また、ガイドラインを守るためには、自院内での確認体制の構築や、制作会社・専門家との連携も重要です。広告効果と法令遵守は対立するものではなく、伝え方を工夫すれば両立が実現できます。ルールを正しく理解し、共感を生む言葉を選ぶことで、信頼と成果の両方を築けます。
clinicHPでは、医療広告ガイドラインに準拠したコンテンツ制作はもちろん、SEO対策から運用サポートまで一貫して対応しています。長く成果を出し続けられるサイトをご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。