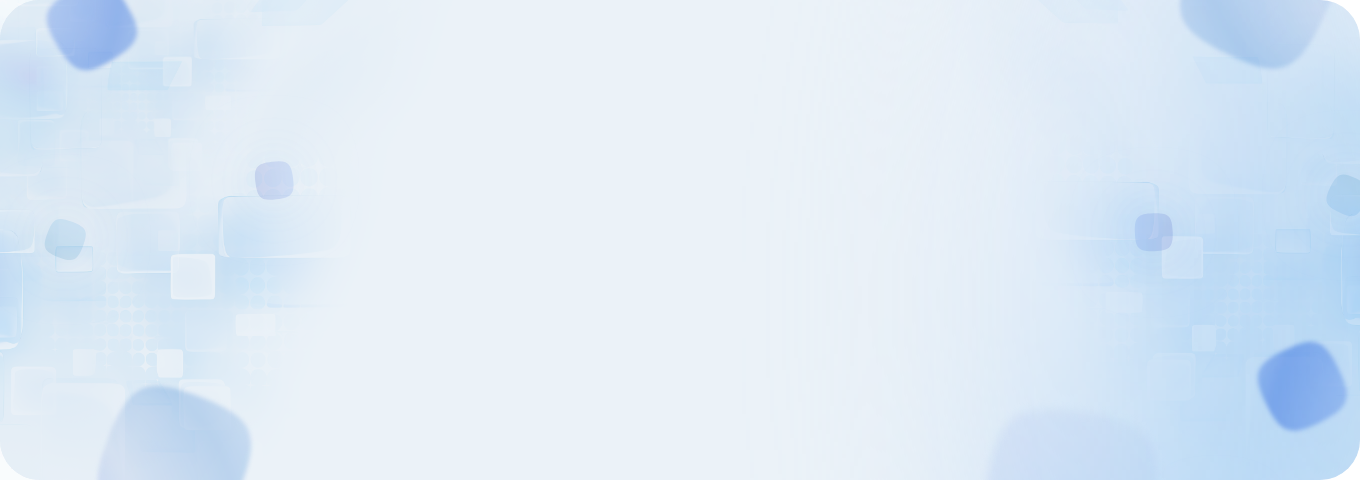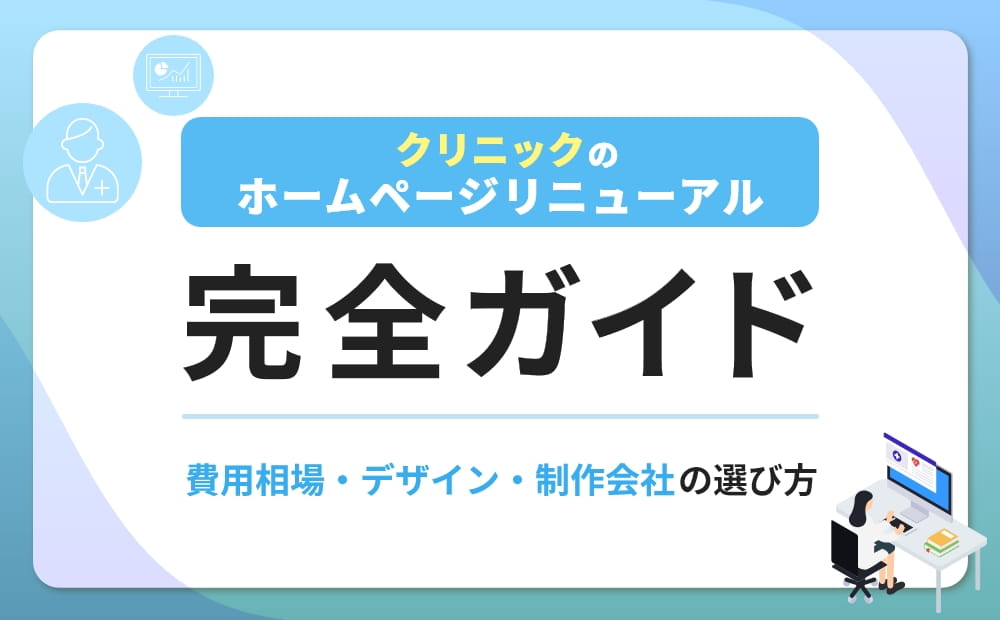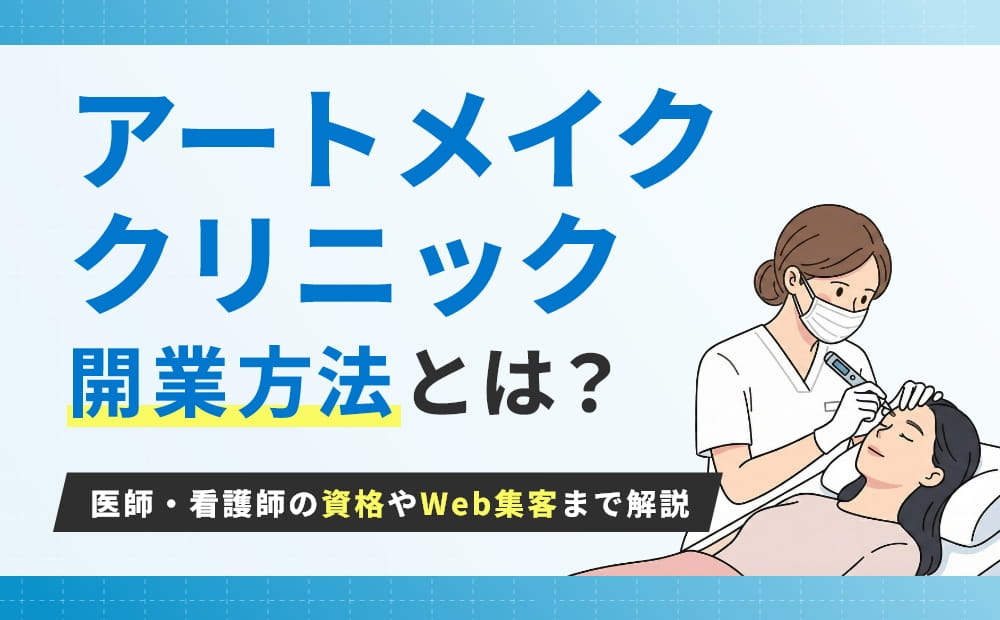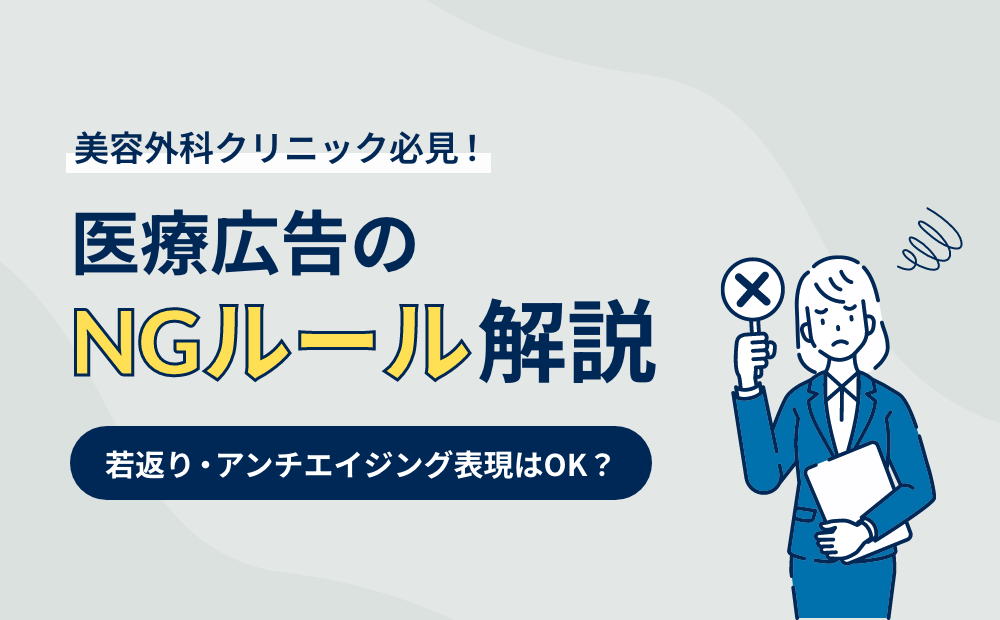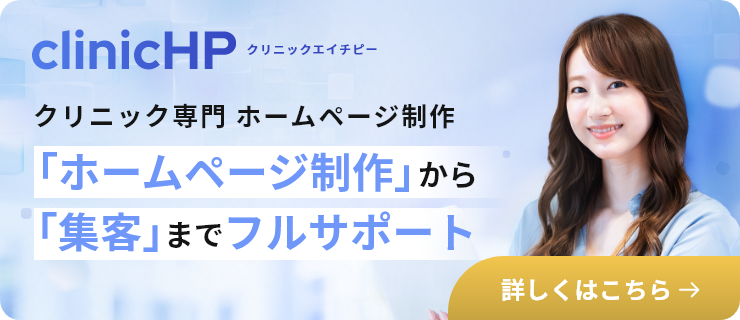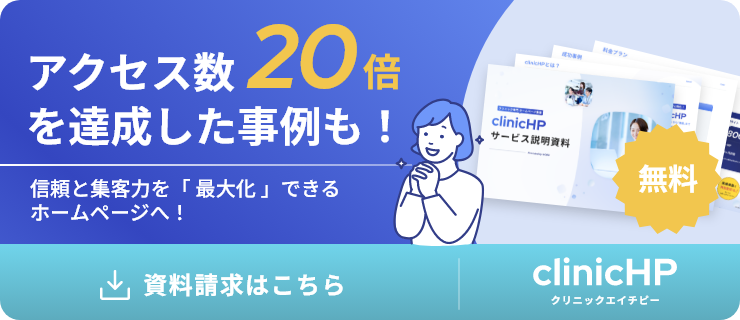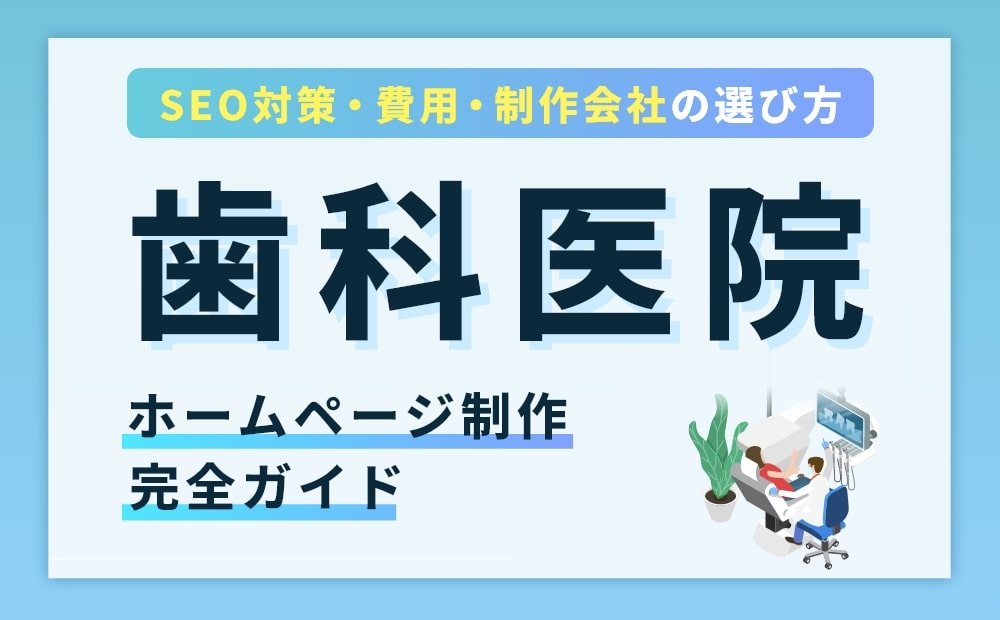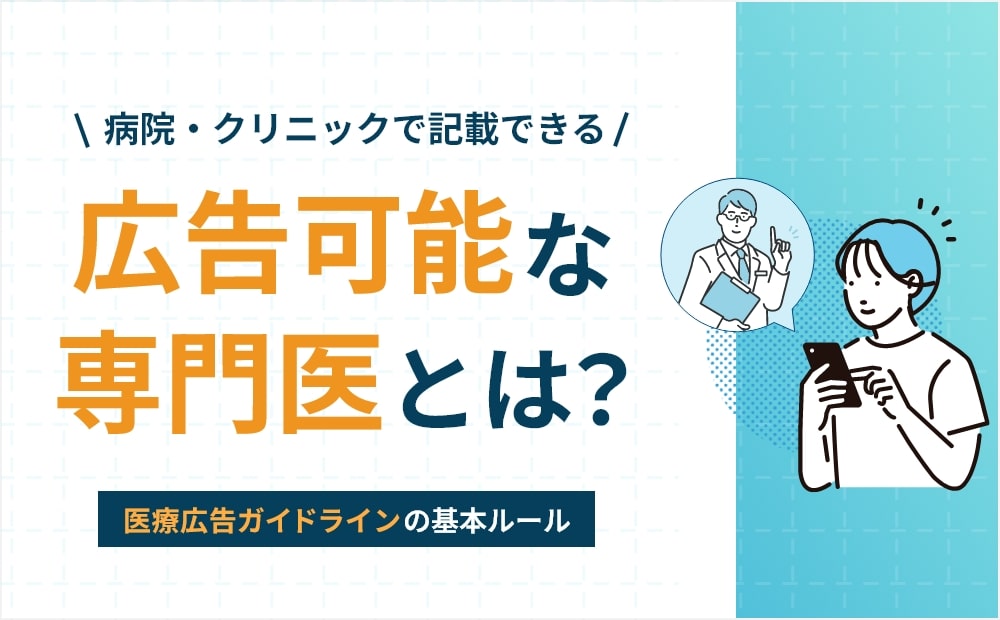クリニックSEO対策の始め方と外注判断の基準【自由診療対応】

クリニックの集患を考えるとき、「SEO対策は必要なのか」「どのように進めればよいのか」と疑問を持つ方は多いでしょう。
特に自由診療を含む医療機関では、広告規制の影響もあり、検索からの自然な流入を安定させることが難しくなっています。
本記事では、SEOの基本的な考え方から地域や症状を組み合わせた具体的な施策、内部・外部対策、MEO、さらにYMYLや医療広告ガイドラインに沿った運用方法まで幅広く整理しました。
院内でできる範囲と外注判断の基準も紹介し、信頼性を担保しながら継続できるSEOの進め方をわかりやすく解説します。
目次
クリニックのSEO対策の基本

クリニックの集患を考えるとき、SEO対策は欠かせない要素ですが、特に自由診療を扱う場合、広告だけに依存するのはリスクがあります。
この章では、SEOの基本概念とクリニックに特有の背景、さらにリスティング広告との違いを整理します。
導入の判断材料になれば嬉しいです。
SEOとは?クリニックに必要な理由
SEOとは、検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)を意味し、Googleなどで上位に表示されるための取り組みです。
なぜ必要かといえば、「患者が診療科や症状で検索した際に見つけてもらいやすくなる」からです。
広告と異なり、情報資産として長期的に効果を発揮できる特徴があります。実際に上位に表示されることで信頼度が高まり、自然な集患につながるためクリニックの認知度を高めたい経営者にとって、SEOは検討すべき基本施策といえます。
自由診療クリニックに特有のSEO課題
自由診療の分野は、保険診療に比べ広告規制が厳しく患者の検索行動も「治療名×地域」といった具体的な形が多く見られます。
例えば「二重整形 新宿」や「薄毛治療 大阪」といった検索で、検索結果で適切に情報を届けられないと、集患の機会を逃すことになります。
また、競合が多い都市部では上位表示の難易度が高くなりやすい点も課題です。東京や大阪などの大都市では、同じ治療を扱うクリニックが多数存在し、上位を争う状況が生まれています。
年々増え続けるクリニックの中に埋もれてしまわないためにも、単に記事数を増やすのではなく、広告ガイドラインに沿った正確な情報を発信していきましょう。
SEOとリスティング広告の違い
SEOは成果が出るまでに時間がかかるものの、検索上位を獲得できれば継続的に閲覧されやすく、資産として積み重ねられる特徴があります。
リスティング広告は即効性があり、設定後すぐに表示される点が強みですが、広告費をかけ続けなければ表示されず、予算に依存する課題があります。
クリニックの集患を考える際には、長期的にはSEO、短期的には広告という役割の違いを理解しておくと良いでしょう。
どちらかではなく、両者を併用することでより安定した集患につなげられます。
クリニックSEOを具体的に紹介

SEOの基本を理解したうえで、実際にどのような施策に取り組むかを、地域名や症状を掛け合わせたキーワード設定、内部・外部のSEO施策、さらにMEO対策について具体的に紹介し、実務の進め方を解説します。
地域名+診療科で対策する際の考え方
「地域名+診療科」の検索は来院を検討する患者が多く使います。
例えば「渋谷 内科」「池袋 皮膚科」といった検索は受診意欲が高いのでこうしたキーワードを狙う際には、診療科ごとの専用ページを作り、診療時間・アクセス・担当医のプロフィールを明確に記載しましょう。
診療方針や検査内容などをわかりやすく整理することで、検索者が安心して受診を判断できるページになります。
症状キーワードを組み込むときの工夫
前述した、「地域名+診療科」とは違い、「地域名+症状」で検索する人は、診療科をまだ決めていない段階です。
例えば「新宿 頭痛」「横浜 シミ」などの検索が該当します。この層に向けた記事では、症状の一般的な説明に加え、受診の目安や相談可能な診療科を示しましょう。
さらに、症状に関するQ&A形式(例:頭痛が続くときは何科に行けばよい?)や、生活上の工夫(例:頭痛なら水分補給や睡眠環境の見直し、シミなら紫外線対策)を簡潔に加えると滞在時間が伸びやすくなります。
医療広告ガイドラインに触れないように断定的な表現を避けつつ、正確で役立つ情報を盛り込むことで、検索者の安心感を高め、自然な集患につながります。
内部SEOの基本(構造・内部リンク)
内部SEOは、サイト全体を整えることで検索エンジンに評価されやすくする施策です。
内部SEOの具体例
- サイト構造を整理する
トップページから診療科ページ、さらに症状別記事へスムーズにたどれるリンク設計にする。
例:「皮膚科トップ → ニキビ治療ページ → 生活習慣に関する記事」 - モバイルの最適化をする
スマートフォンで見やすいレスポンシブデザインにする。
例:小さな画面でも文字が読める・予約ボタンが押しやすい。 - 表示速度を改善する
画像を圧縮したり、不要なスクリプトを減らす。
例:トップページの写真を軽量化して読み込みを早くする。 - 内部リンクを工夫する
関連するページ同士をつなげる。
例:「内科ページ」から「高血圧に関する記事」へリンクを設置。
これらは患者の利便性を高めると同時に検索評価の安定につながります。
なお、サイト構造は制作会社、内部リンクの工夫はSEO会社と分けて依頼すると連携が複雑になりやすいため、一貫して対応できる会社に任せると効率的です。
外部SEOと被リンク戦略の注意点
外部SEOとは、他のサイトから自院サイトへリンクを貼ってもらい、検索エンジンからの評価を高める取り組みです。
医療分野では、リンクの数よりも「どのサイトからのリンクか」という質が重視されます。
例えば、医師が学会や医療情報サイトに記事を寄稿し、その記事からリンクを得る方法があります。
また、自院サイトで統計データや調査結果を公開すれば、他のメディアに引用されリンクされることもあります。このように役立つ情報を発信することで、検索エンジンと患者の双方から信頼を得やすくなります。
自然に紹介される形を目指しましょう。
MEO(ローカルSEO)での集患強化
MEO対策とは、Googleマップや検索結果の地図上で自院を見つけやすくする取り組みです。
特にクリニックでは、Googleビジネスプロフィールを活用することが基本となります。
住所や診療時間を正しく登録し、院内やスタッフの写真を最新の状態で掲載すること、さらに口コミの更新や返信を継続することが信頼につながります。
これらを整備すると、検索エンジンからの評価も高まりやすくなりますし、来院前の患者に安心感を与えられます。
自由診療クリニックのように競合が多い環境では、MEOを実践することが地域で選ばれるきっかけとなります。
次の章では、クリニックの集患戦略に直結する「YMYL」と「広告ガイドライン」に配慮したSEO運用について解説します。
YMYL・広告ガイドラインに沿ったSEO運用の基本

医療情報は「YMYL」と呼ばれる厳格な領域に含まれ、検索エンジンから特に厳しく評価されます。
この章ではYMYLの意味と注意点、一次情報の活用方法、E-E-A-Tを高める工夫、さらに医療広告ガイドラインに沿って記事を作成するための具体的なポイントを整理します。
YMYLとは何か?医療SEOに影響する理由
YMYLとは「Your Money or Your Life」の略で、人生や健康、経済などに大きな影響を与える情報領域を指します。
例えば「糖尿病の治療法」や「美容外科の施術内容」といった情報は、誤ると患者の行動に悪影響を及ぼすため、Googleは特に正確性を重視しています。
クリニックのSEO記事で「必ず治る」といった断定的な表現を使うと評価を下げる要因になります。
一次情報の活用がSEOで信頼を高める
医療分野のSEOでは、根拠が明確な一次情報を使った記事が評価されやすくなります。
一次情報とは、学会の診療ガイドライン、厚生労働省の統計、学術論文、医師による監修コメントなどです。
例えば「高血圧の診療指針は日本高血圧学会のガイドラインに基づく」と記載すれば、記事の信頼性を検索エンジンに示せます。
自由診療でも「日本美容外科学会の資料に準拠」と出典を明示すれば、専門性や正確さが伝わりやすくなりGoogleの評価基準であるE-E-A-Tを強化し、検索順位を安定させる効果につながります。
E-E-A-Tをクリニックサイトで担保する方法
E-E-A-Tは「経験(Experience)」「専門性(Expertise)」「権威性(Authoritativeness)」「信頼性(Trustworthiness)」を示しており、Googleが医療を含む重要な情報領域で特に重視している評価基準です。
クリニックのサイトでも、この基準を満たすことで検索順位が安定しやすくなります。
- 専門性の明示:執筆者の資格や専門分野を記載する
例:「執筆者:皮膚科医/日本皮膚科学会認定医」 - 監修体制の表記:記事に医師が監修として関わっていることを明記する
- 権威性の補強:診療実績や研究活動を診療科ページに掲載する
- 信頼性の確保:住所・連絡先を正しく表示し、診療内容を正確に整理する
コラム記事なら、冒頭や末尾に執筆者・監修医の情報を記載し、本文で学会資料や統計を引用します。記事の最後に住所や連絡先を明示すれば、E-E-A-Tを自然に満たせます。
医療広告ガイドライン違反を避ける注意点
医療広告ガイドラインでは、誤解を与える表現が禁止されています。
具体例として「必ず治る」「最先端で唯一の方法」といった断定表現、患者体験談の掲載などです。ビフォーアフター写真についても原則は規制対象ですが、施術内容・料金・リスク・副作用を併記すれば限定的に認められる場合があります。
SEO記事を安全に運用するには、「当院では○○に対応しています」と事実を客観的に伝えること、さらに「参考:厚生労働省〇〇ガイドライン」といった出典を明記することが基本です。
これにより検索エンジンに正確な情報として評価されやすくなり、長期的な順位安定につながります。
自院での運用と外注判断のポイント

SEOは一度で完結する施策ではなく、継続的な取り組みが求められます。自院で対応できる範囲と、外部に任せるべき領域を分けて考えることが基本です。
この章では、院内で実施できる範囲の判断基準、外注先の比較ポイント、費用とROIの考え方、そして外注を成功させる準備について解説します。
院内でSEOを実施できる範囲の判断基準
SEOは記事制作やキーワード選定、サイト構造の改善など多岐にわたります。
自院で対応できるかどうかは、担当者の知識や業務負担によって左右されますが、定期的に記事を更新できる人材がいれば自院で内製化は可能です。
ただし、キーワード選定や表示速度の改善、内部構造の調整など技術的な施策、医療広告ガイドラインへの対応を含めるとかなり難易度は高くなります。
まずは、院内で無理なくできる部分を明確にし、それ以外を外注に任せる形が現実的です。
SEO会社に依頼する際の比較ポイント
外注先を選ぶ際には、医療分野での実績や広告ガイドラインへの理解度を必ず確認しましょう。
料金体系や契約形態を比べるだけでなく、どのような方法でSEOを行うのかを具体的に質問すると安心です。
また、成果を測定するための指標(例:検索順位、アクセス数、問い合わせ数)を共有できるかどうかも重要です。透明性のある会社を選び、長期的に信頼できる関係を築きながら安定した集患につなげましょう。
外注費用とROIを判断するための視点
SEOの外注費用は月額で数万円から数十万円まで幅があります。
判断の際は金額だけに注目せず、どの程度の成果が期待できるかをROI(投資対効果)の視点で考えることが大切です。
例えば「月○件の問い合わせ増加につながるか」という基準で評価すると判断がしやすくなります。
短期的な費用よりも、長期的に患者数や来院率にどう寄与するかを見極めましょう。
また、クオリティや対応力も重要で、自院の一員のように伴走し、コンテンツの充実や構造化データ・画像作成(シェーマなど難易度の高い画像)まで対応できる会社を選ぶことが望ましいです。
安さだけで判断すると成果につながらないリスクが高まります。
外注を成功させるためのクリニック側の準備
外注を円滑に進めるには、クリニック側の準備も重要です。
まず、自院の強みや診療科ごとの特徴を整理し、外部パートナーに正確に伝えられるようにしておきましょう。さらに、記事作成やサイト改善に必要な情報を提供できる体制を整えておくと、外注の効果を高めやすくなります。
任せきりにするのではなく、定期的に進捗を共有しながら取り組むことでSEO施策が実際の集患につながりやすくなります。
よくある質問
クリニックのSEOについて、よく寄せられる疑問をまとめました。
効果が出るまでの期間やMEOとの違い、広告ガイドライン対応、小規模クリニックでの活用、SNSとの組み合わせ方を簡潔に解説します。
SEOの効果はどれくらいで出る?
SEOの効果が表れるまでには一般的に3〜6か月程度かかります。
検索順位の変動や競合状況によって期間は異なり、短期間で成果が出ることは少ないです。中長期的に記事を更新・改善し続けることで、検索結果の上位に安定して表示されやすくなり、集患につながる可能性が高まります。
MEOとSEOはどちらを優先すべき?
地域密着型で近隣からの来院を増やしたい場合はMEOが有効で、診療科や自由診療の施術名などで広く検索流入を得たい場合はSEOが適しています。
多くのクリニックでは両者を併用していますが、優先度はクリニックの目的に応じてバランスを取るのが現実的です。
SEOで広告ガイドライン違反になることは?
SEO記事にも広告ガイドラインは適用されます。
禁止されているのは「必ず治る」といった断定的表現、体験談の掲載、ビフォーアフター写真の使用などです。違反すると行政指導や記事修正が必要になる場合がありますのでSEOを行う際は、事実に基づき客観的かつ正確な情報を記載しましょう。
小規模クリニックでもSEOで成果は出せる?
小規模クリニックでもSEOを正しく実践すれば成果は十分に期待できます。
特に「地域名+診療科」や「地域名+症状」といったキーワードで上位表示を狙うと、来院につながる検索に届きやすくなります。大きな広告予算がなくても、情報を整理し定期的に発信を継続することで、検索順位の向上と集患効果を少しずつ高められます。
SEOとSNS施策をどう組み合わせる?
SEOとSNSは役割が異なりますが、組み合わせると効果的です。
SEOは検索ニーズに応える形で集患につながりやすく、SNSは情報拡散やブランディングに強みがあります。記事でまとめた情報をSNSでシェアしたり、SNSでの質問を記事化するなど連携させると、集客チャネルを広げながら相乗効果を生み出せます。
戦略から制作・運用まで一貫支援するclinicHPの強み

SEOは単体で取り組むよりも、戦略立案から制作・運用までを一貫して行うことで成果につながりやすくなります。clinicHPでは包括的な支援体制でご支援します。
院内リソースだけでは難しい部分も含め、計画から実行までをワンストップで支援できる体制を整えています。制作や記事執筆の段階から医療広告ガイドラインを遵守し、リスクを抑えながら発信を行います。さらに自由診療に特化した実績をもとに、治療名や地域性を踏まえた集患設計を行い、競合が多い都市部でも最適化が可能です。
加えてMEOやリスティング広告との連動支援により、SEOだけでなく検索全体を見据えた集患強化を実現します。一元化された体制だからこそ、複数業者に分ける必要がなく、情報共有や費用の面でも効率的に進められます。
まとめ
クリニックのSEO対策は、集患を安定させるうえで欠かせない取り組みです。
まずは基本を理解し、地域名や症状を組み合わせたキーワード設計、内部・外部施策、MEOなどを組み合わせて実践することが求められます。
さらに、医療分野特有のYMYLや広告ガイドラインを意識し、一次情報の活用や監修体制を整え、検索エンジンからの評価と信頼性を高めましょう。
自院で対応できる範囲を見極め、必要に応じて外注を取り入れることも有効です。記事で得た知識を行動に移すことで、持続的に患者に選ばれる環境を築きやすくなります。
資料請求・相談のご案内
SEO対策を含む集患の取り組みは、長期的に見てクリニック経営に大きな影響を与えます。
しかし、施策の範囲が広いため、自院だけで完結させるのは簡単ではありません。
株式会社NOBUが提供するclinicHPでは、戦略立案からWebサイト制作、SEO、広告運用までを一貫してサポートしています。医療広告ガイドラインに準拠した情報設計を徹底し、自由診療を含む幅広い診療科の集患にも対応可能です。